コンビニまで車で10分かかる程度の田舎の出身です。
今と違ってどの家庭にもネット環境があるわけではなく、最大の娯楽と言えばテレビ。
そんな前時代の終わりかけを感じる港町で、母はよく私たち姉弟を市立図書館に連れて行ってくれました。
カウンターで本を返却したら、真っ先に赤いカーペットが敷かれた絵本コーナーに駆け込みます。
座り込んで本を読んだり、読み聞かせの会を楽しんだりしたものです。
私はお気に入りの本をずっとリピートするタイプの子供で、2・3冊の決まった本を繰り返し母に借りるようにせがんでいました。
母としてはもっといろんなジャンルに目を向けてほしかったと思いますし、「またぁ?」と言われたことも何度もあったと思いますが、ちゃんと借りて私を満足させてくれましたね。
自分で選んだ本だけではなく、母はアンパンマンの紙芝居や他の絵本も一緒に借りてくれました。
そしてそれらを寝る前に私たちに読み聞かせてくれました。
紙芝居の時は体育座りで母の前に座り、絵本の時は布団の中で母の隣を姉弟で分け合い、お話が終われば天井照明を夕焼けにしてお休みなさいです。
両親も子供のためだけではなく自分のために図書館をよく利用する人で、父は時代小説を読み漁っていましたし、母は手芸の本を借りていたように思います。
まぁ、そんな家庭環境だったので、本好きな子供が育つのは必然だったのでしょう。
保育園での必然
もちろん保育園での読み聞かせの時間も、自分で読むのも大好きでした。
当時から走る系は全般苦手で、砂場遊びや室内遊びをしたことばかり覚えています。
そしてあれは年長さんの時、教室でみんなと何か作るか、描くかしていました。
早く終わった人は好きなことをしていいとのことだったので、先に終わらせた子たちと一列に整列して絵本を読んでいました。
その様子が先生のツボにはまったらしく、とても楽しそうに笑ってくれたのです。
大好きな先生が本を読んでいたら笑ってくれた。
保育園児がさらに本に夢中になるには、十分すぎる切っ掛けでした。
当時から、先生が面白かったのは「園児が自発的に真っ直ぐ行儀よく並んでいたこと」であり「本を読んでいたこと」そのものではないと分かっていましたが、「本を読む=嬉しいこと」と刷り込まれてしまったんですね。
もちろん良いことです。
私の幼少期で妹弟の誕生と並ぶ、人生のターニングポイントでした。
だからヒロコ先生、ありがとうございました。
読み聞かせについて厚かましいお願い
以上、私の幼少期の思い出から考えた「読書にドはまりした土壌と切っ掛け」のお話でした。
ここで日々お子さんに読み聞かせをしているご家族に、幼少期の私を代弁してお願いです。
私が読み書きを覚え、ある程度文の意味を理解し、語感というものを感じとれるようになってきた頃のこと。
当時家にあった中で、お気に入りの絵本は「絵本版 蜘蛛の糸」と「三年寝太郎」でした。
なぜ好きだったか。それは話が長かったからです。
早く寝たい母にとっては避けたい絵本だったでしょう。
でも、子供にしてみればお話の時間が長く続いてくれる嬉しいアイテムでした。
感覚的に楽しい時間が増えると分かっていたのかもしれませんね。
なのでお子さんの要求に懲りずに、頑張って読んであげてください。
出来れば、面倒な様子は出さずに。
・・・申し訳ありませんけど、追加で。
「しろいうさぎとくろいうさぎ」も大好きだったのですが、その絵柄が暗めだと気付いたのは成人してからでした。
そう、割と絵は気にしていないお子さんもいます。
「こっちの明るい方にしなさい」とか多分違いが分からないかもしれないので、飽きるまで好きにさせておいてくれると嬉しいです。
今度こそ以上。では本日の読み聞かせ、楽しんでください。
では。
v1.png)
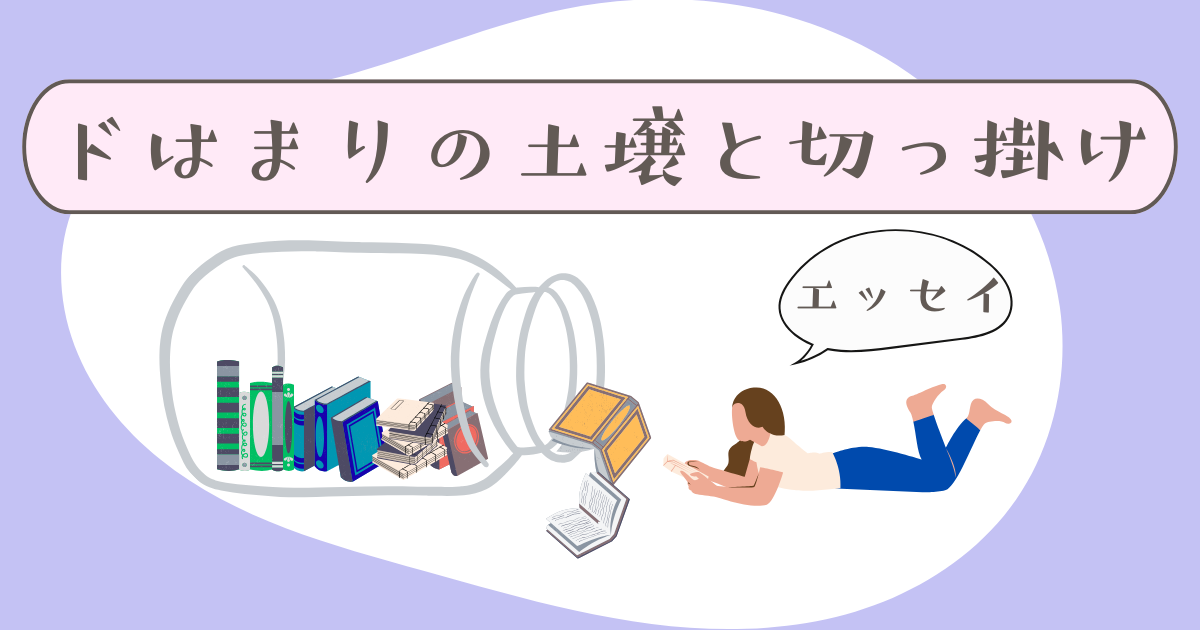
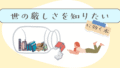
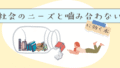
コメント