「好き」を言語化する技術
推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない
三宅 香帆[著]
切っ掛けの本
今回ご紹介する本は、私がブログを開設する切っ掛けとなった本です。
それまでブログ運営については、薄っすらとしか関心がなかったのですが、この本を読み終わってから実行してしまうほどにやる気が湧いてきました。
もっと具体的に心情の変化を並べると、
・自分にもこんなに好きなものがあったと自覚した
・「好き」を形に残すことは、自己肯定感が上がると気付いた
・好き嫌いは気軽にしていいと思えた
そんな風に思えたのです。
多くの情報に埋もれがちな「自分の声」を磨きぬいて輝かせる。
その手助けをしてくれる本のご紹介です。
準備が大事
「『好き』を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに『やばい!』しかでてこない」では、推しの魅力を「自分の言葉で」発信するための具体的なノウハウを学ぶことができます。
序章に続いて「推し語りとは」から「準備段階」へ続き、その後に「お喋り」「SNS」「文章」の3つのカテゴリーにおける具体的手法が解説されています。
その読みやすく分かりやすいこと!!
ノウハウ本として圧倒的な説得力を持っています。
私は「推し語りとは」で一気に文章に引き込まれたのですが、それは「妄想だから、正しくなくていい」とはっきり書かれていたからです。
ハードルが下がって気が楽になりましたし、そもそも感想に「間違い」など無いのでしょう。
そして続く「準備段階」の中では、「他人の感想を見ないこと」が重要であるとされています。
この情報化社会。レビューやコメント、考察であふれていますよね。
ぼんやりとSNSを眺めていたら流れ弾を食らった気分になったことも割とあります。
でも、それで推しへの愛の解像度が曇るのはもったいない。
一歩引いて自分の感想を優先することで自衛しましょう。
推しのためなら割と簡単にできてしまうかも?ですよ。
土台はすでに
続く「お喋り」「SNS」「文章」の実践の章。
「お喋り」では相手との距離感の、「SNS」では自衛と主張の、「文章」ではゴール設定の大切さが目立って印象に残りました。
共通項もありましたが、こうして書き起こしてみると結構違いがありますね。
私は「文章」に興味をひかれて、この本を購入しました。
しかし3つの章を読んでいるうちに、「具体例すべてに心当たりがあるぞ?」と驚きました。
読んでいるうちに「あ~、あの時上手く説明できなかったなぁ」とか、「あのコメント、だからムカついたのか」とか、「あの説明文、もう少しああすれば良かった」といった記憶と反省が浮かんできました。
「好き」を言語化する技術は非常に実用的な技術であると思います。
真っ平らな土台から組み立てていくものではなく、すでにある経験を活かして修正することで、どんどん精度を向上させることが出来そうです。
より良く伝えられるようになって過去の後悔を成仏させたい。
そして「好き」を飛び切り輝かせたい。
あのほろ苦い記憶も、丸ごと更新できてしまうかもしれませんね。
「好き」を写真のように
この本を読み終わった後、「自分が形に残しておきたい『好き』は何だろう」と考えました。
私にとってそれは「本」でした。
さらに試しに「伝えたい本」をリストアップしていくと、その場で思いついただけでも200冊以上のタイトルが出てきたのです。
自分でも「こんなに?!」と驚きましたが、それら全ての「好き」が形に残ることを空想すると、「自分にはこんなに沢山素敵なものが詰まっていたのか」と誇らしくなりました。
「準備」の章には、「『好き』は、一時的な儚い感情である。」とあります。
そこからイメージしたのは写真です。
「好き」を一枚一枚写真に残す。
やがてアルバムとなり、本棚になり、図書館になるかもしれません。
道のりは長そうですが、なかなかロマンのある夢ができたと思います。
あなたの「好き」は何ですか?
一緒に埋もれるほどの「好き」を感じましょう!
ではまた。
v1.png)
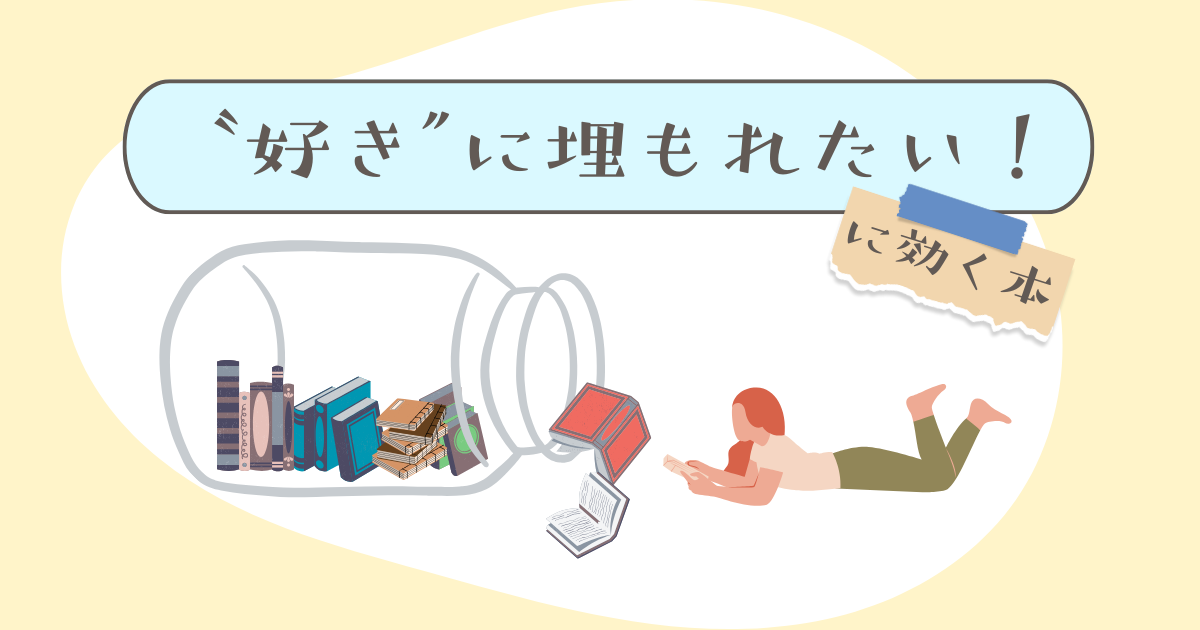
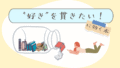
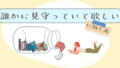
コメント