陰翳礼讃
谷崎 潤一郎[著] 大川 裕弘[写真]
郷愁の薄闇
丈夫さと風情を併せ持つ「古民家」。
燻した柱や精緻な細工の鴨居に、憧れを持つ人も多いでしょう。
しかし古い家の弱点と言えば「暗さ」と「寒さ」です。
実家がいわゆる古民家だったのですが、天井が高く壁も白くなかったので外が晴れるほど家が暗く感じたものです。
しかし今の明るく真っ白な壁紙の明るい部屋にいると、子供のころ当たり前にあった薄闇を懐かしく感じることもあります。
今日はそんな「くらがり」の美学を現代に伝える名著の紹介です。
湿りある美
「陰翳礼讃」は「痴人の愛」「春琴抄」などで知られる谷崎 潤一郎先生が執筆した、日本人の美学・美意識についての随筆集です。
日本建築や工芸品、和食などを通じて語られる西洋文化との差。
それらが纏う陰翳の魅力について先生の考えが述べられています。
様々な出版社から世に出されている名著ですが、私はパイ インターナショナルから出版されている一冊を推薦します。
その理由は、文章とともに大川 裕弘さんの写真を使用していること。
水墨画のような陰影に映える小物や蠟燭の炎、植物などの色彩。
晩秋の冷えた空気のように凛々しい写真たちが本文と引き立てあい、完成された美術書のようです。
書店でコントラストの強い表紙に一目ぼれして購入した一冊なのですが、2018年初版にもかかわらず、今も全く古さを感じさせない洗練された仕上がりだと感じます。
流れるような文章にしっとりとした空気が写真によって加わり、雨の日の冷えと湿気の中で文に浸っているような郷愁に似た感覚が味わえます。
元祖 お籠り
私が本書で一番印象に残っているのは「されば日本の建築の中で、一番風流に出来ているのは厠であると云えなくはない」という部分です。
実家のトイレは真ん中から追いやられたような角の位置にあり、夜は不気味なうえ寒さ暑さがダイレクトに伝わる場所でした。
とても風流などとは言えない場所に感じますが、谷崎先生が想定するのは母屋から廊下を伝って行き、周りを植栽が囲む切り離されたような場所にある厠。
そんな静かで清潔で、自然に囲まれながら籠ることが出来る場所として描写されています。
「私はそう云う厠にあって、しとしとと降る雨の音を聴くのを好む」とまであり、谷崎先生は厠で自然に親しんでいたようです。
普段は特に意識すらしない現代のトイレ。
ここに籠ることが好きな人は割といると聞きますが、それは狭く物が少ない空間が落ち着くからではないかと想像します。
部屋が薄暗いと、自分も周りの空気に混ざるような、存在感が薄くなるような気になったことがあるのは私だけでしょうか?
先生は落ち着く空間で感覚を絞り、自然に親しんでいたのでしょうか。
谷崎先生が厠を不浄の場所ではなく瞑想部屋のように捉え、そこに日本人の美学を見出していたのは、私たちの先祖もそういった場所として捉えていたからなのかと想像が広がります。
美意識の教科書
日本人らしい湿り気を持った美学を教えてくれる「陰翳礼讃」。
起床から就寝に至るまで明るい場所で過ごすことが多い現代で、暗がりがもたらす癒しを教えてくれます。
今日は部屋の明かりを間接照明ひとつにして、陰翳を感じてみませんか?
ではまた。
v1.png)
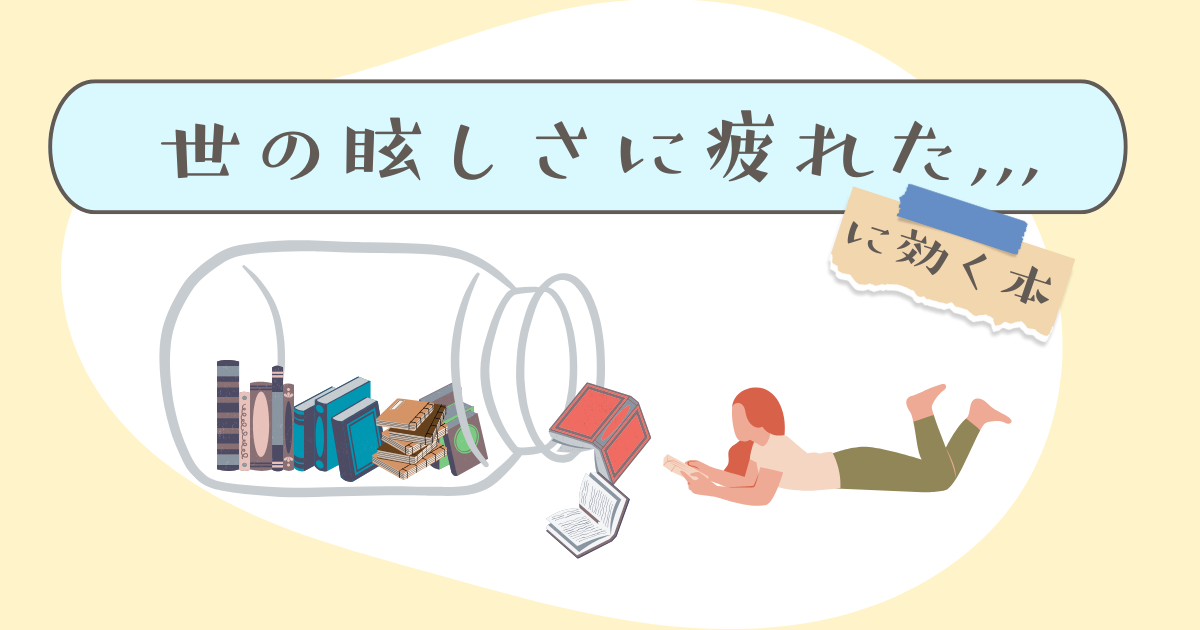
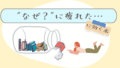
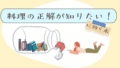
コメント