良い質問を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた
「なぜ」と聞かない質問術
中田 豊一[著]
「なぜ?」の弊害
「なぜなぜ分析」をご存じでしょうか。
言わずと知れた自動車メーカー「トヨタ」発祥の「根本問題解析」の手法のことです。
言葉通り、発生した問題に対して「なぜ」を3回から5回繰り返すことで原因を究明していくのですが、これはあくまで「モノ」や「システム」に有効な方法。
人同士で「なぜ」をやると、「聞かれたので自分なりに理由を説明したら怒られた」「相手の間違いを改善したいのに伝わらない」といったディスコミュニケーションを起こしてしまうことがあります。
「『なぜ』と聞くと反発される」と思う人は、「『なぜ』なぜがダメなのか」を知りましょう。
「なぜ」と聞かれることに疲れた人は、「なぜ、あの人は『なぜ』と聞くのか」を知りましょう。
今日は、そんな悩みを持つ人たちに役に立つ、「なぜ」と聞かずに原因を探る質問術が学べる本をご紹介します。
必要な本は光って見えます
「良い質問を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた『なぜ』と聞かない質問術」は、20年近く発展途上国援助の現場で活動してきた中田 豊一(なかた とよかず)さんの著書です。
同じく支援活動にかかわってきた和田 信明さんの「どんな相手とも正確に意思疎通する知的コミュニケーションの技法」を「メタファシリテーション」として共同で体系化し、現在はこの技法を伝えるべく活動しておられます。
本書では「なぜ」を使ったコミュニケーションは「思い込みを引き出す」として、「なぜ」を使わずに事実を引き出す手法が実例をもとに分かり易く解説されています。
私がこの本を手に取ったのは、まさに「なんで」と聞かれることに悩んでいた時期でした。
「相手が知りたいのはこういうことだろう」と考え答えるのですが、そこで相手の質問の意図と齟齬が生じ、結果、答えたのに怒られるといったことが度々起こっていました。
「そもそも相手はなぜ『なんで』と質問してくるのか」と思っていたところこの本に出会い、「なぜ」を使うことによって起こる弊害と実践的なノウハウを知ることができました。
それによって「同じ轍は踏むまい」と自身の戒めになると同時に、自分から会話する際の確認事項について意識が高まり、自衛にも繋がったように思えます。
立場にかかわらず、より良いコミュニケーションを築くための指南書であり、日ごろの会話を顧みる気づきの書でもあるのです。
「事実」に注目!
本書では「なぜ分析」は相手が問題分析への強い意欲を持っているときや聞き手に対する信頼と尊敬がある場合は有効であるとしています。
その一方で、「なぜ質問」は力関係がある、またはモチベーションに差がある場合、より「会話のねじれ」を生み出しやすいともしています。
そんな事態を避けるために重要なのが「事実質問」です。
「答えが一つに絞られる質問」と定義され、「いつ」「どこ」「何」「他に」といった事実を質問することで、相手の認識を引き出し、自分の認識との差を埋めていきます。
本書の第1章から第3章までは、この事実質問の手法を例文を用いて解説されており、実際の会議や教育、日常会話まで、自分の生活の中で実践するイメージがつかみやすいと感じました。
その中でも特に有難かったのが「『思い込み質問』を『事実質問』に変換するワーク」です。
普段しがちな会話の癖を自覚・修正する訓練になり、いざ実行する際の自信に繋がります。
著者の「本気で生活に役立てて欲しい」という熱意が伝わる箇所の一つであり、「本当に身につくだろうか」と心配する気持ちを持つ人には実に手厚い心遣いであると感じました。
実例多数の優しい指南書
この本を手に取る人は、私のように「なぜ質問」で嫌な思いや歯がゆい思いをした人や、いまいち教育が上手くいっていないと感じる人が多いでしょう。
そういった様々な立場の人たちに対して有効な守備範囲の広いこの一冊。
きっと、あなたのお役に立つと思いますよ。
ではまた。
v1.png)
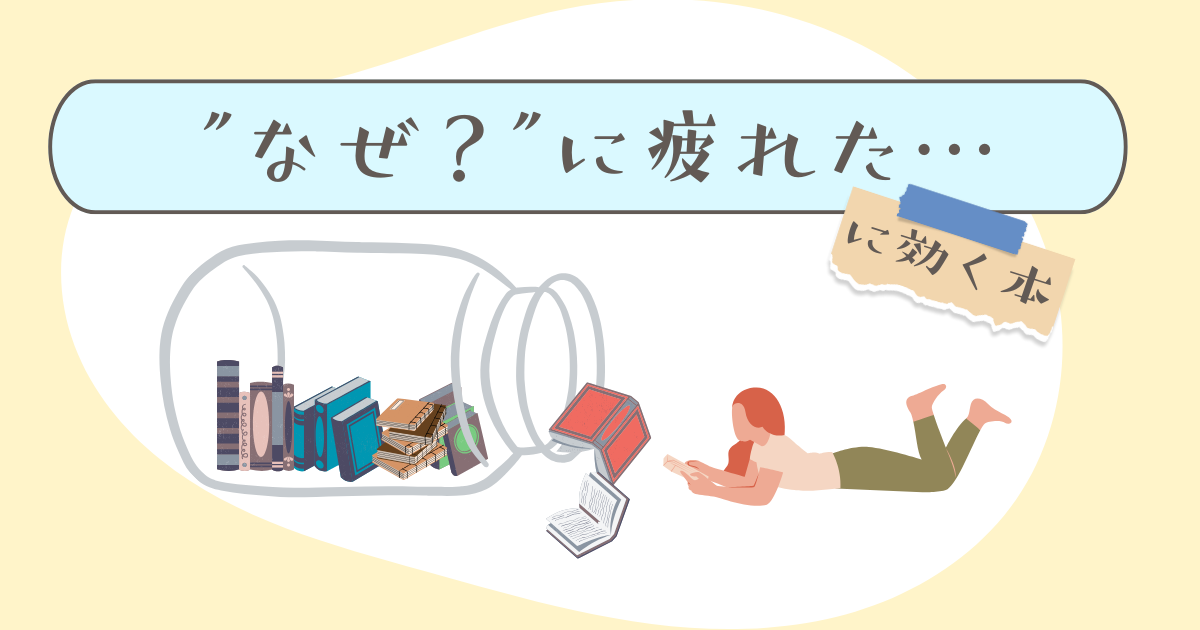


コメント